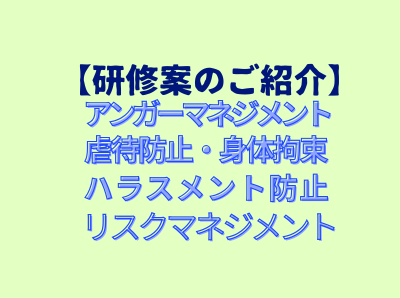
2025年10月24日
介護・障がい福祉の現場では、支援者が利用者の尊厳を守るために日々努力を続けています。
しかし近年、職員による虐待や不適切ケアが全国で報告され、厚生労働省は法令を改正して防止体制の強化を進めています。
令和6年度改定では、高齢・障がいの両分野で**「虐待防止委員会の設置」「指針整備」「研修の実施」「担当者の設置」が義務化され、体制未整備の場合には減算や行政指導の対象**となります。
本研修は、福祉現場で働くすべての職員が、制度を正しく理解し、日常業務の中で「虐待を生まない職場文化」を根づかせることを目的としています。
虐待は特別な職場で起こるものではなく、「日常の延長線上」で生じる行為です。
人員不足や支援の難しさ、コミュニケーションの行き違い、感情労働の蓄積など、福祉現場には誰もがストレスを感じやすい構造があります。
「忙しいから後で」「これくらいは仕方ない」といった小さな見過ごしが、不適切ケアや虐待の芽になります。
たとえば――
高齢者施設で「まだ食べてないの?」と急かしてしまう
障がい者支援施設で「どうせ分からない」と声かけを省略する
夜勤帯で、職員同士のイライラが連鎖する
こうした行動は意図的でなくとも、**「支援者中心の関わり」**に偏る危険があります。
本研修では、10の事例を通じて、グレーゾーンを職員全員で考える対話型ワークを行い、気づきを共有します。
「これは誰のための支援か?」を常に問い直す姿勢を育てます。
本研修「虐待防止の体制づくりとその取り組み」は、法制度・体制整備・感情マネジメントの三つの柱を組み合わせた実践的プログラムです。
1⃣ 虐待防止とはなにか
→ 高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法を比較し、共通点と相違点を理解。虐待の5類型(身体的・心理的・性的・経済的・放置)を具体例で整理します。
2⃣ 令和6年度改定による防止体制の動向
→ 委員会・指針・研修・担当者の4要件をわかりやすく整理し、行政監査で指摘されやすいポイントを解説。
3⃣ 体制づくりと文書化の手順
→ 委員会メンバー構成、開催頻度、記録様式、指針の書き方を実例で紹介。理念文ではなく行動指針=実務基準として機能させる方法を学びます。
4⃣ 一人ひとりの実践と感情ケア
→ 虐待防止には、制度整備と同時に「支援者の心の安定」が欠かせません。アンガーマネジメントやセルフケアを取り入れ、怒りや苛立ちを安全に手放す技法を体験します。
また、小規模事業所や併設法人でも導入しやすい合同研修・伝達研修のモデルを提示し、職員全体で共有できる体制づくりを支援します。
虐待防止は、「チェックリストで管理すること」ではなく、**「支援のあり方を見つめ直すこと」**から始まります。
制度上の整備と同時に、職員一人ひとりが「利用者の尊厳を守る意識」を持ち続けることが何より重要です。
本研修では、高齢・障がいの両領域に通じる視点から、
制度理解+職員研修+感情マネジメントの一体的なアプローチで、防止と定着の両立をめざします。
📌 研修のご相談はこちら
研修プログラムの詳細やお見積りは、[お問い合わせフォーム]からお気軽にご連絡ください。
➡ [研修シラバス一覧ページへ]
(筆:ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表 梅沢佳裕)