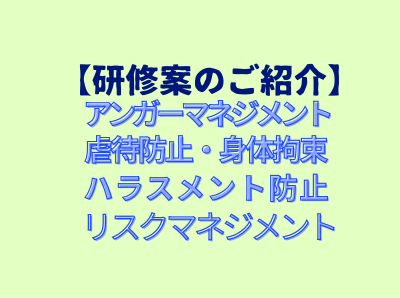
2025年10月21日
介護職は、頭脳労働でも肉体労働でもなく、第三の労働と呼ばれる「感情労働」に従事しています。
「笑顔で接しなければならない」「怒ってはいけない」という使命感のもとで、自分の感情を抑え込み続けると、心のエネルギーが消耗していきます。
実際、全国で報道される介護・障害者支援施設での虐待事件の背景には、職員のストレスや怒りのコントロール不全が関係していることが多く、現場の人手不足や夜勤の連続も拍車をかけています。
「こんなことでイライラする自分が嫌になる」「もう限界だと思うことがある」――
そんな声は特別なものではなく、誰もが抱える自然な感情です。
問題は“怒ること”ではなく、怒りに振り回されること。この違いを理解し、整えることが現場を守る第一歩です。
本研修「ストレスケアとアンガーマネジメント」は、理論と実践を融合した感情マネジメント研修です。
プログラムは以下の4部構成で進行します。
【タイトル】メンタルケアとアンガーマネジメント
【研修時間】およそ90~180分
【対象者】高齢者介護・障がい者支援事業所の対人援助職(看護職・介護職など)
《研修プログラム案》
1️⃣ 介護職のメンタルケアの必要性
→ 感情労働の構造を理解し、ストレスのサインを早期に察知する方法を学びます。
2️⃣ アンガーマネジメントと怒りが生まれるメカニズム
→ 「~べき」というコアビリーフ(自分の中の正義)が怒りを生む仕組みを解説します。
3️⃣ アンガーマネジメントの3つのコントロール
→ 衝動・思考・行動を整理し、6秒ルールやマインドフル呼吸で冷静さを取り戻す方法を実践します。
4️⃣ 職場で取り組むアンガーマネジメント
→ チーム全体でイライラを共有し、感情の見える化を進める「アンガーログ」の導入を提案します。
また、現場事例(夜勤中の連続コール対応)をもとにしたロールプレイを通じて、
「怒りの奥にある潜在的な感情」――“分かってほしい”“助けてほしい”という本音――に気づくワークも行います。
単なる理論ではなく、翌日から現場で使えるスキルとして定着する構成です。
介護職が長く安心して働くためには、心のセルフケアが欠かせません。
本研修は、感情を我慢するのではなく、上手に扱うためのトレーニングです。
怒りを抑えるのではなく、「怒ってもいい、でも後悔しない怒り方を選べる自分になる」――
この考え方が、チームの雰囲気を変え、虐待防止や離職防止にもつながります。
📌 研修のご相談はこちら
研修プログラムの詳細やお見積りは、[お問い合わせフォーム]からお気軽にご連絡ください。
➡ [研修シラバス]
■最新介護情報Blog【介護キャンパス】研修内容の一部をご紹介しましょう!※外部リンク
【法定研修】 ストレスケアとアンガーマネジメント(第1部)
― 感情労働の時代を生き抜く介護職の“こころの整え方”
【法定研修】ストレスケアとアンガーマネジメント(第2部)
― 業務でイライラしてしまった時に直ぐに実践できる感情コントロール法
(筆:ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表 梅沢佳裕)